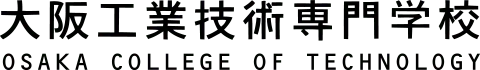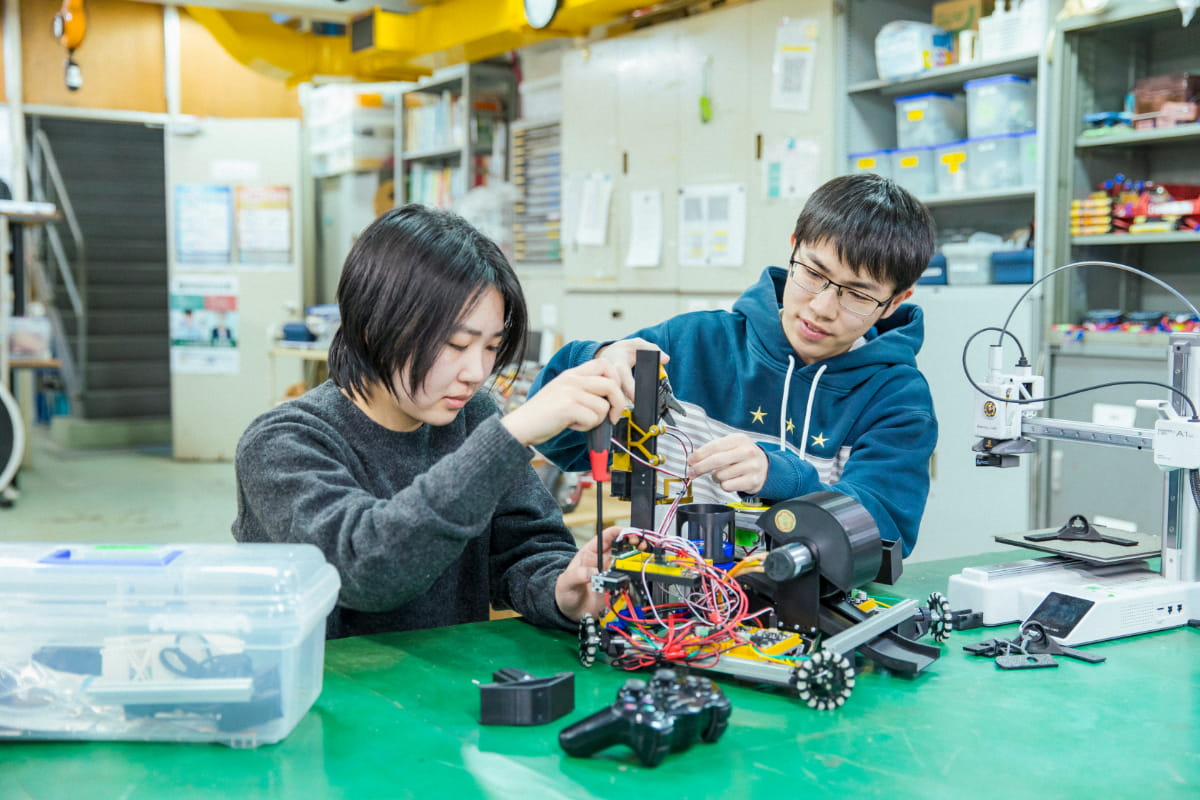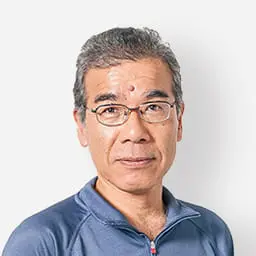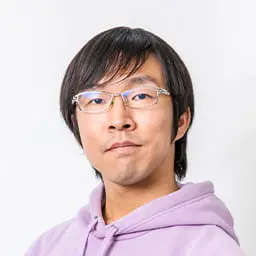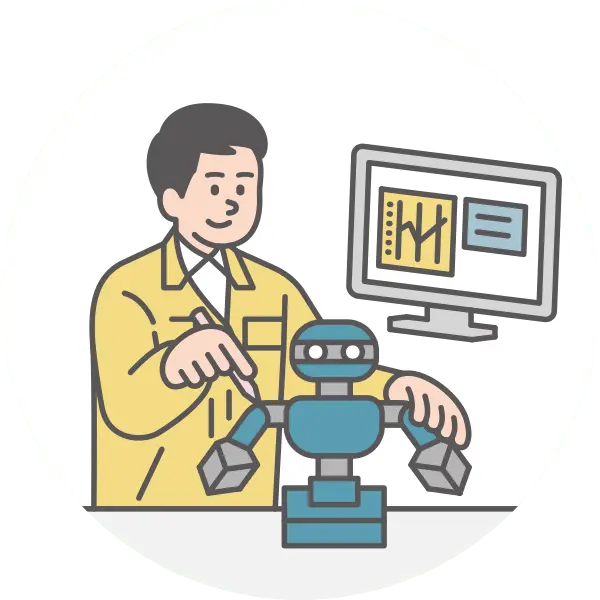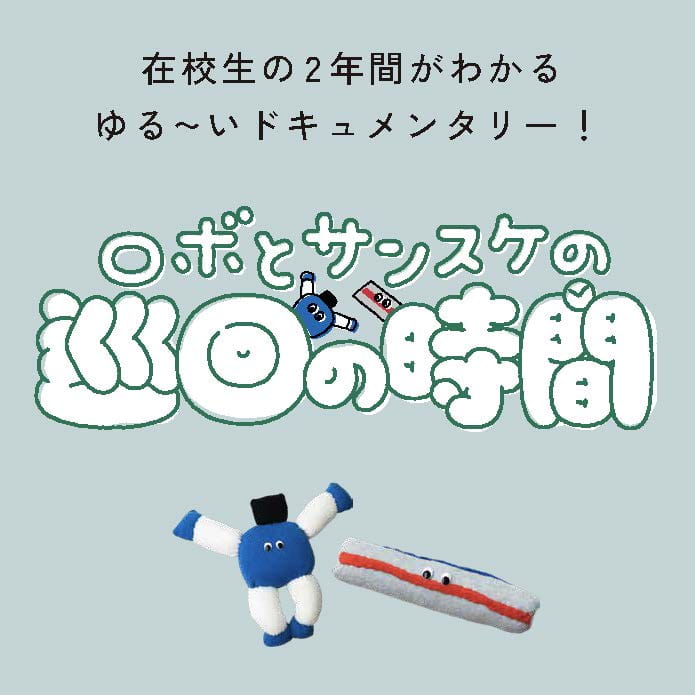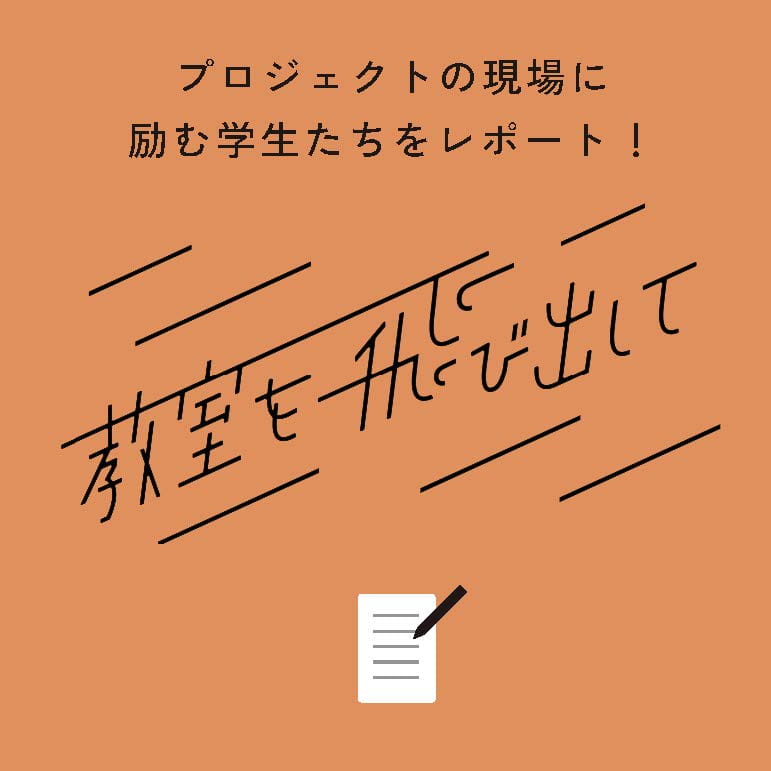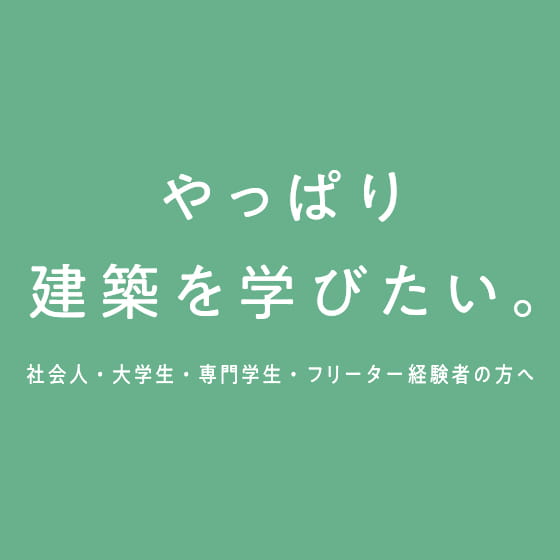ロボット・機械学科
ロボット・電気機械・電子の専門性を育み、
プロとしての仕事力を身につけます。
卒業後の進路
設計士(ロボット・機械・電気・電子回路) 生産・製造 工業デザイナー 機械メンテナンス など
こんな力が
身につきます!
- 設計から製造に至る
機械設計の知識・技術 - 工作機械の操作や素材加工など、
製造現場に欠かせない専門技術 - 電子、半導体、回路などの
基幹技術、センシング技術
ロボット・機械学科の特徴
1
ロボット機械・電気に特化した
2分野の専門科目で、社会を担う技術者へ!
ロボットコンテストに向けて、製作工程を学びます。CADで設計し、NC工作機器・3Dプリンタを用いて機械を開発するほか、電子回路を組み立て、マイコンでプログラミングを経験。機械製図や機械設計技術者の資格取得も目指します。
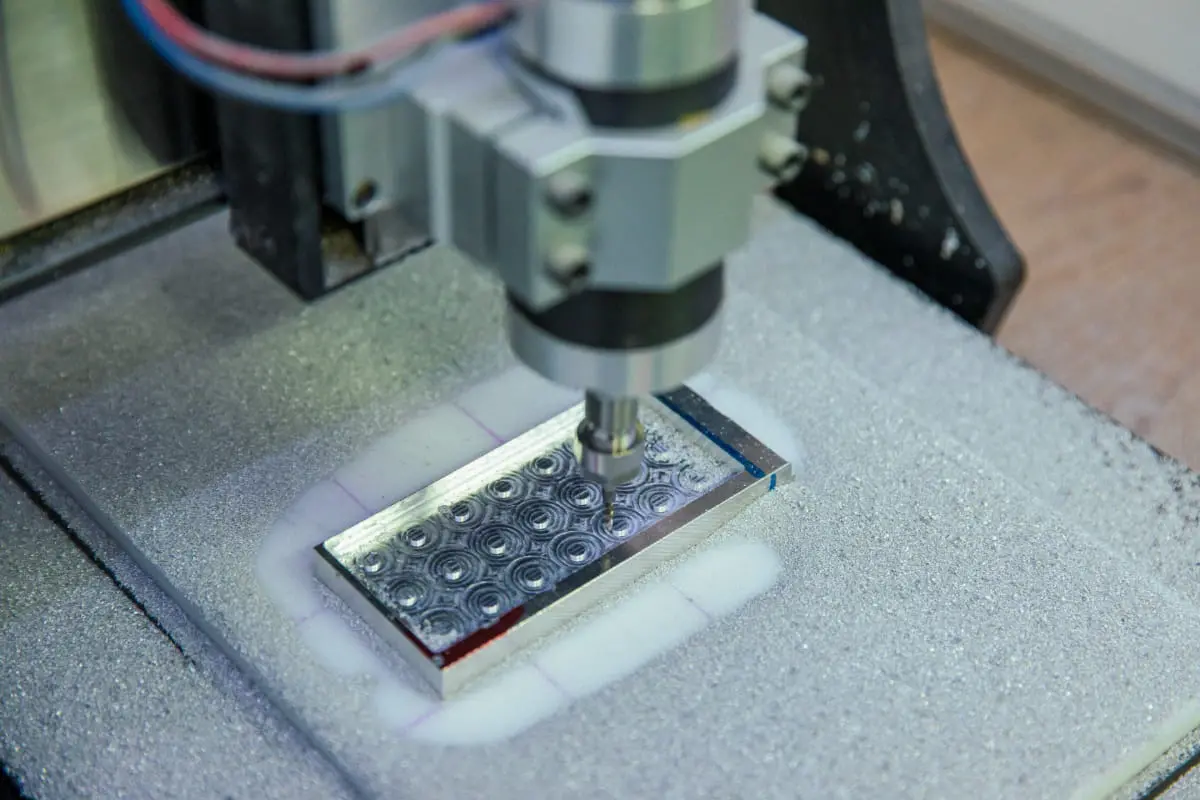
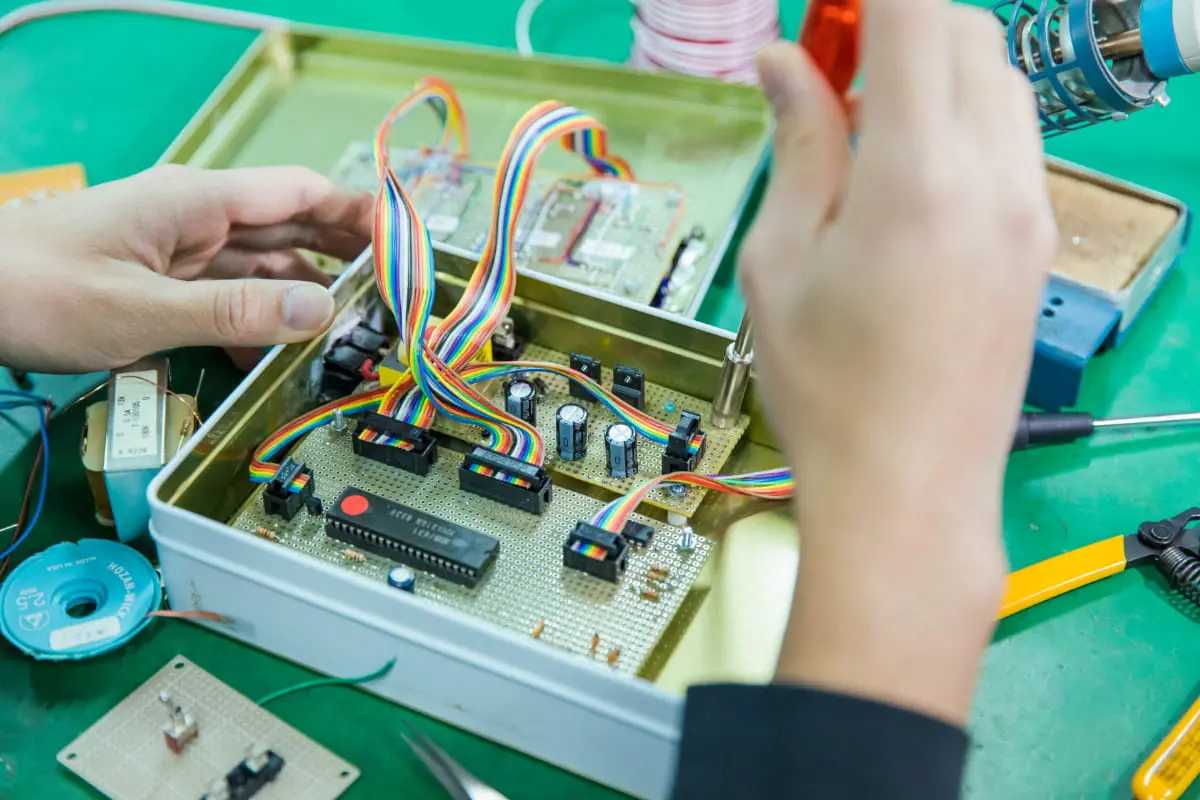
2
プロの道を歩む先輩が、
キャリアアップを支えます!
ロボット機械業界を担うエンジニアが、
時代を見据えた指導を行います。
株式会社カンセツ所属

先生が手がけた仕事

3
ロボットコンテスト・
競技会にも出場できます!
ロボット・機械学科では、培った学びを試す機会として、毎年、ロボットコンテストや競技会に出場。限られた製作期間のなかで、仲間とチームワークを実践し、創造性と技術の向上を図っています。
出場実績
・ ROBO-ONE
・ キャチロボバトルコンテスト
・ つやまロボットコンテスト
・ OECU杯ヒト型レスキューロボットコンテスト
・ 近畿学生2足歩行ロボットリーグ
・ Honda エコマイレッジチャレンジ鈴鹿大会
ロボット・機械学科

2年間の学びのながれ
1年次
-

前期
電気・機械の基礎理論を学ぶ
生活のあらゆる場面で使われる電気・機械。1年次前期は専門用語や製図技術の基礎を学び、工業数理や力学、材料など幅広い知識を身につけます。
-

後期
将来の仕事を見据えた分野選択
1年次後期は、ロポット機械・電気分野いずれかの科目を選択。キャリアデザインを視野に入れ、さらに専門性を高めながら学びを探究します。
2年次
-
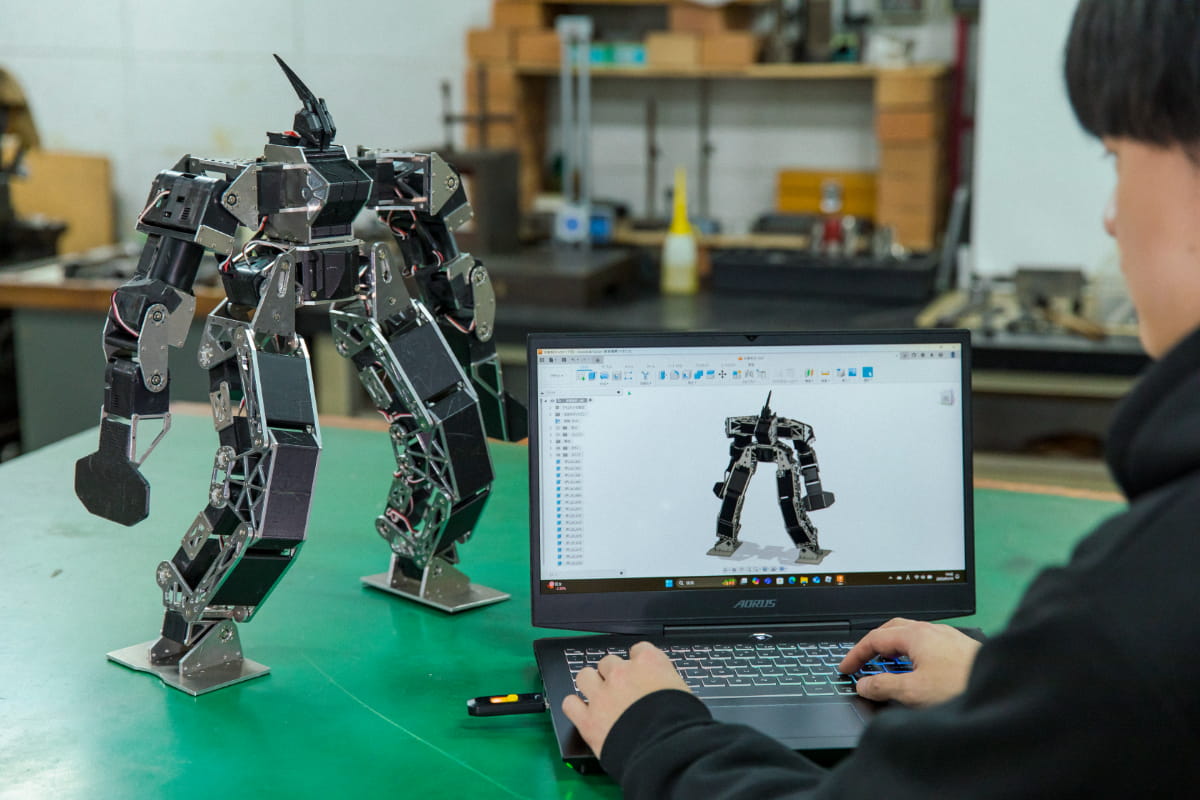
前期
実務に生きる設計力を養成
1年次に学んだ知識・技術を応用し、ロボット・家電・機械の構造理解を深めながら、現場で求められる2D・3D設計を実践的に習得します。
-

後期
ものづくりを追求する力を育む
グループワークで卒業制作に挑戦。社会で仕事をする上でのチームビルドを疑似体験しながら、プロジェクトマネジメント能力を育成します。
授業紹介
製作実習 I
ロボット機械分野では、NASAの火星探査機などに採用されているロッカーボギー機構を用いたロボットを開発中! また、電気分野ではデジタル回路を学び、ものづくりの基本を体得するために、デジタル時計を各人で製作します。
活躍する卒業生
ロボット・機械学科の活動を
Instagramで発信中!
機械製図や工作、電子回路やロボットの製作といった実習、座学の授業風景をご紹介。行事やイベントの様子も随時更新しています。ぜひチェックしてください!